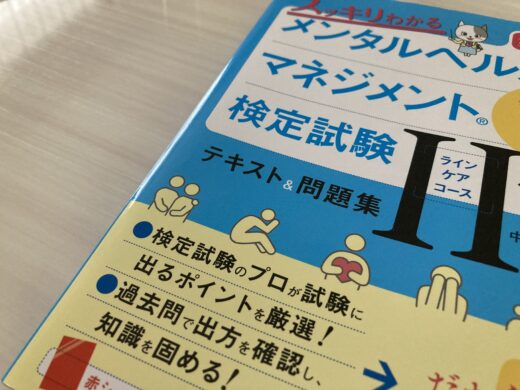メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種の申し込みをしました。
試験日は11月3日。
あと1ヶ月ほどですが、正直まだ知識が定着しておらず不安もあります。
ただ、申し込み締切が9月26日だったので、覚悟を決めて本格的に取り組むしかありません。
メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種とは?
この検定は、メンタルヘルスケアに関する基礎知識を学ぶもので、
資格取得自体で職業の選択肢が広がるというよりも、
自分自身や部下・同僚の不調にどう対処するかを学ぶ内容になっています。
テキストを読み進めていくと、
体調の変化や不調のサインを察知し、適切に対応する方法、
さらには必要な情報にどうアクセスするか、といった実践的な知識が得られる印象です。
個人的には、もっと「ストレスによって体調がどう変化するのか」や「その変化にどう対応すればよいのか」といった、もう少し前段階のことに興味がありました。
ストレスと身体の関係に興味を持ったきっかけ
そもそもこの検定を勉強しようと思った理由は、
「ストレスが自分の体にどう影響しているのか」を知りたかったからです。
たとえば、
- 電車に乗っていると喉に違和感を感じる(気道が狭くなる感覚)
- 仕事のことで不安なことを考えていると、急に満腹になり食べられなくなる
僕自身は、こうした反応を以下のように仮説立てています:
- 騒音がストレッサー → 身体的ストレス反応で気道収縮 → 喉の違和感
- 不安がストレッサー → 胃液の分泌抑制 → 油ものが飲み込めなくなる
いずれも個人の仮説に過ぎませんが、
こうした反応が起きた時にどう対処すればよいのかを知りたいと思っています。
また、そもそもなぜ騒音や「先行き不安」がストレッサーになるのか、
その原因をどう特定するのかにも関心があります。
ちなみに騒音については、
スマートウォッチでストレスレベルを測定するまで自覚していませんでした。
こうした気づかないストレッサーが、日々蓄積されていくんだろうなと感じます。
おわりに
この検定に合格したからといって何か劇的に変わるわけではないかもしれませんが、
ストレスやメンタルヘルスに向き合う第一歩として、大きな意味があると思っています。
そもそも勉強に対してコンプレックスがありましたが、それを乗り越えたいという気持ちもあって、この挑戦を始めました。
この記事では「なぜストレスに興味を持ったのか」を深掘りしようと思っていましたが、
それはまた別の記事でまとめてみようと思います。
今振り返って思うこと(2025年5月)
振り返り
当時は、ストレスに対する興味とペーパーテストへのコンプレックスから、チャレンジしてみようという気持ちで検定試験を受けることにしました。
学生時代はあまり感じなかった(あるいは気づかなかった)ストレスですが、社会人になってからは体調に反映されるようになり、それを通してようやく自覚できるようになりました。
ストレスによる健康被害については、専門的な知識がなくても耳にする機会が多く、その怖さは身近に感じていました。
もともとは「自分自身のストレスについてもっと知りたい」という動機で勉強を始めたのですが、実際に学んでみると、内容は“症状が出た後”の対応方法が中心で、「ちょっと違うかも」と感じる場面もありました。
それでも興味が途切れることはなく、そのまま試験を受けました。
あれからどう変わったか
学生の頃と違って、今はある程度読書習慣がついていることもあり、テキストを読み進める中で「活字に慣れてきたな」という実感がありました。
メンタルヘルスに関する知識が直接的に仕事に活かされているかどうかはさておき、職場の同僚に対する見方が少し柔らかくなったように思います。
👉 関連記事はこちら
 0.5ミリ先
0.5ミリ先